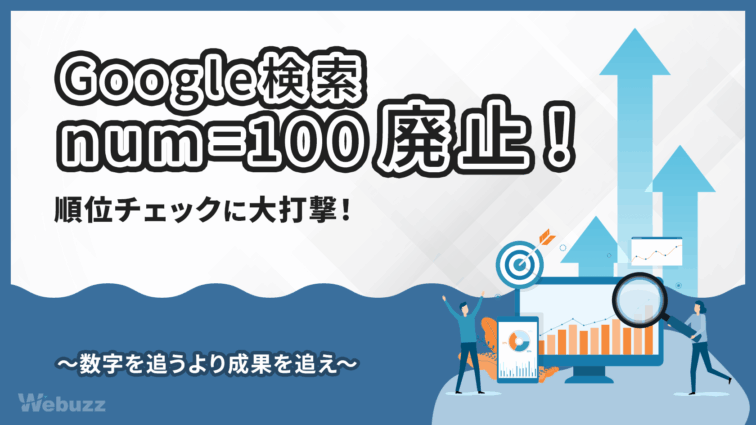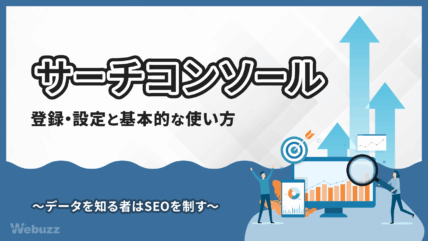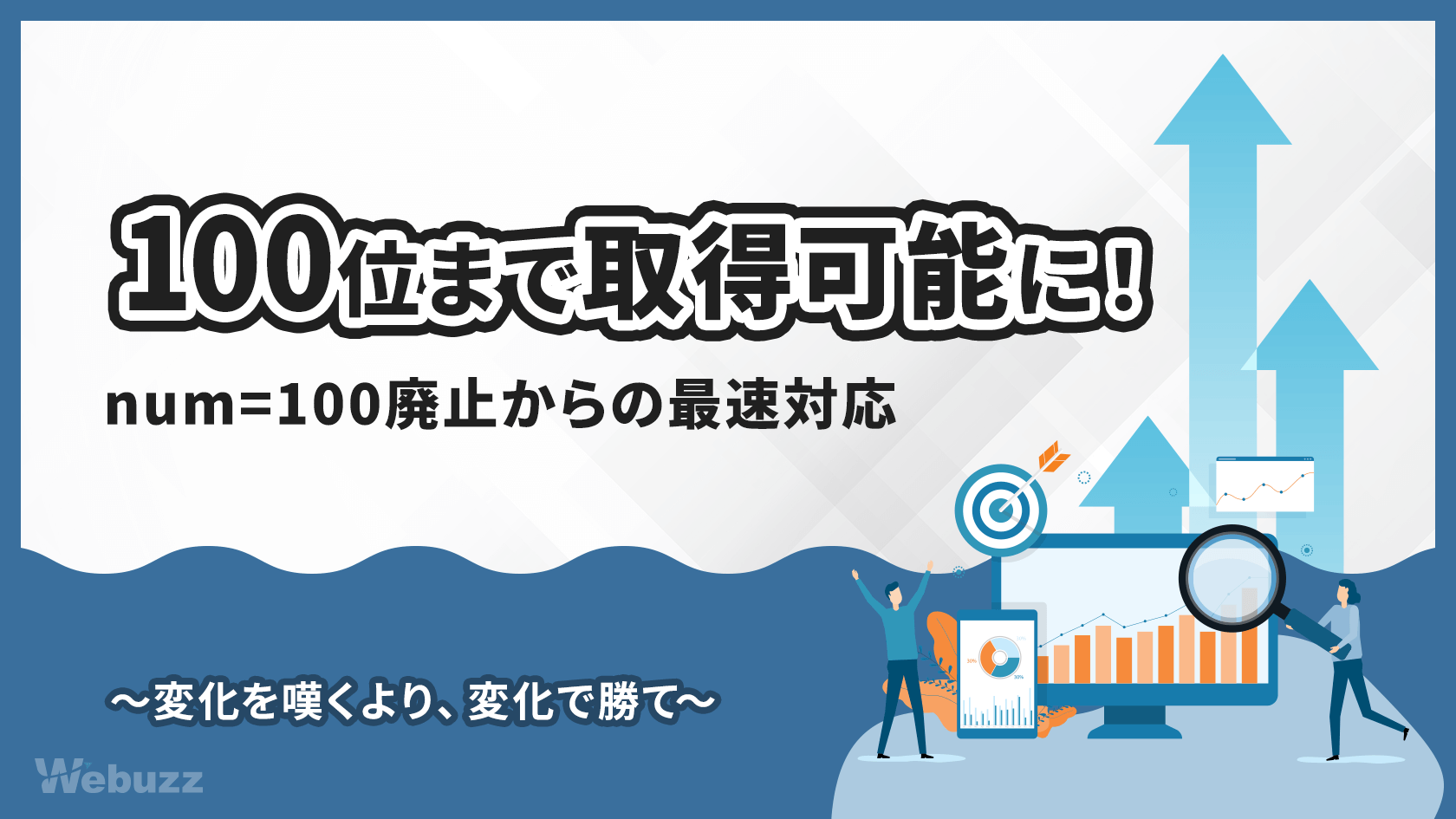【追記】2025年10月21日 更新
検索順位チェックツール「ノビリスタ(Nobilista)」が、Google検索のnum=100廃止による取得制限に対応し、「毎日1〜100位までの順位データ取得」を実現したと発表しました。
詳しくは以下の速報記事で解説しています。
ノビリスタが100位まで取得可能に!num=100制限を突破
Google検索の順位チェックで長年使われてきた「検索結果を100件まとめて表示するパラメータ(num=100)」が、2025年9月中旬、突如として使えなくなりました。
これにより「検索順位チェックツール」や「検索順位を100件まで確認していたユーザー」に大きな影響が出ています。
さらに、この変更は単にツールの利用制限にとどまらず、Google Search Console(サーチコンソール)の数値にも変化をもたらしています
インプレッション数の急減や平均順位の改善といった現象が起き、「サイトの評価が下がったのでは?」と不安になる声も出ています。
本記事では、このnum=100廃止の背景とSEO業界への影響、そして今後どのように対応すべきかを整理して解説します。
もくじ
num=100とは?検索結果100件表示の仕組み
「num=100」は、Google検索のURL末尾に 「&num=100」 と付加することで検索結果を1ページに100件表示させるためのパラメータです。
かつてGoogleの検索設定には「1ページあたりの表示件数」を変更できるオプションがあり、最大100件まで表示可能でした。
しかし2018年頃にUI上の設定は削除され、それ以降もURLの末尾に「&num=100」を付けることで、同じように100件の結果を一度に確認できる“裏ワザ”が残っていました。
この仕組みはGoogle公式が案内していたものではありませんが、2025年まで動作し続け、SEO担当者やアフィリエイターの間で広く利用されてきました。
「num=100」を使えば標準の10件ではなく100件の検索結果が一度に得られるため、検索順位を100位まで一気に確認したり、競合調査を効率的に行ったりする用途に活用されてきたのです。
特に「検索順位チェックツール」や「スクレイピングサービス」はこの仕組みを利用し、1回のリクエストで100位までの結果を収集していました。
通常の10件表示に比べてリクエスト数が10分の1で済むため、コストや速度の面で大きなメリットがあったのです。
廃止の経緯と理由
「num=100」パラメータは、2025年9月中旬に突如として使えなくなりました。
それまで問題なく動作していたのが、ある日から一斉に機能しなくなり、検索結果は強制的に10件ごとの表示に戻されました。
Googleから正式な告知はなく、事前の予告もありませんでした。
ただし海外SEOメディアの問い合わせに対して、Google広報は「そのURLパラメータは正式にサポートされたものではない」とコメントしており、バグではなく意図的な仕様変更であることが確認されています。
では、なぜ廃止されたのでしょうか。
公式な説明は出ていませんが、業界ではいくつかの理由が推測されています。
- 検索体験の統一
- 通常の検索は10件表示が標準です。100件まとめて表示できる特殊な方法を排除し、ユーザー体験を一律にする狙いがあったと考えられます。
- サーバー負荷の軽減
- 1リクエストで100件を返す処理は、10件表示に比べて10倍の負荷がかかります。膨大な検索クエリに対応するGoogleにとって、インフラ保護の観点からも合理的です。
- スクレイピング対策
- Googleの利用規約では、無断の自動検索取得(スクレイピング)を禁止しています 。長年「非公式な抜け穴」として利用されてきたこのパラメータを廃止することで、ランキング計測ツールやボットによる大規模なスクレイピングを抑制しようとしていると見ることができます。
こうした背景を踏まえると、今回の変更は「ユーザーにとっての標準体験を守る」と同時に「Google自身のシステムとデータを保護する」ための措置と見ることができます。
影響1:検索順位チェックツール
「num=100」の廃止は、検索順位チェックツールに大きな影響を与えました。
これまでツールは「1回のリクエストで100件の検索結果を取得」できたため、効率よく順位データを集めることができていました。
しかし現在は強制的に10件ごとのページ表示しかできなくなり、同じ100件を取るのに10倍のリクエストが必要になっています。
その結果、以下のような変化が起きています。
- 取得コストの増加
- ツール側は今までより多くのリソースを消費するため、サーバー負荷やAPIコストが増えました。今後、利用料金の値上げや無料プランの制限強化につながる可能性があります。
- データ取得の遅延
- これまで一瞬で取れていた順位データも、ページを何度も巡回する必要があるため処理速度が落ちています。大量のキーワードを一度に追跡する場合、更新に時間がかかるようになりました。
- ツール各社の対応
- 主要な検索順位チェックツールはすでに「10件ごとにページを分割して取得する方式」へ移行し、表面的には従来通り100位まで確認できますが、裏側では負担増を抱えています。また、DataForSEOなど一部のAPIサービスでは課金単位を「100件あたり」から「10件あたり」に変更する対応も行われ、利用者側のコスト増加が現実的な問題となっています。
利用者にとってはすぐに使えなくなる心配はありませんが、ツールのレスポンスやコストに影響が出てくる可能性があることを理解しておく必要があります。
影響2:Search Consoleの数値変動
「num=100」廃止の影響は、検索順位チェックツールだけではありません。
サーチコンソールのレポート数値にも顕著な変化が見られました。
特に多くのサイトで報告されているのが、次の2つの現象です。
- インプレッション数の急減
- これまで「100件表示」で拾われていた下位順位(30位以降など)の表示回数が一気にカウントされなくなり、多くのサイトでインプレッション数が大幅に減少しました。ある分析では、調査対象の約320サイトのうち87.7%でインプレッションが減少、77.6%で検索クエリのユニーク数が減少したと報告されています。
- 平均掲載順位の改善
- 下位の結果が除外されたことで、計算上の平均順位が押し上げられています。実際には順位が上がったわけではなく、多くのクエリがページ3(30位)以降に表示されなくなったように見えるだけです。
このため、2025年9月中旬以降のデータは、それ以前と単純に比較できなくなりました。
「インプレッションが減った=検索流入が減った」と誤解すると、不必要に不安を感じたり誤った施策につながる危険があります。
実際には、サイトのオーガニックトラフィックが急減したわけではありません。
GoogleのJohn Mueller氏も「実際のクリック数が減っていないのであれば心配する必要はない」と示唆しており、今後はクリック数やCTR(クリック率)など実ユーザーの行動指標に注目することがより重要になります。
今後の対応と運用のヒント
「num=100」の廃止によって、100位までの検索結果を容易に取得する公式な方法はなくなりました。
とはいえ、業界ではいくつかの代替策や対応が模索されています。ここでは現実的な手段と、その限界について整理します。
代替策の限界
Googleは開発者向けにCustom Search JSON APIを提供していますが、1クエリあたり最大10件程度の結果しか取得できず、商用利用にはクエリ数制限や料金が発生します。
そのため、大規模な順位トラッキングへの適用は難しいのが現状です。
一方で、多くのSEOツールは独自のスクレイピングを継続していますが、10件×ページ数で順次取得する方式に切り替わりました。
これは従来比で10倍のリクエストが必要となるため、時間とコストが大幅に増加しています。業界でも「決定的な抜け道はなく、地道にページをめくるしかない」という声が多く聞かれます。
クリックやCTRを重視する流れへ
今回の変更は、SEOレポートの指標を見直す良い機会でもあります。
インプレッションの急落や平均順位の改善は測定方法の変化によるものであり、実際の検索トラフィックが減ったわけではありません。
今後はインプレッションや平均順位といった表層的な数値に依存するのではなく、クリック数やCTR(クリック率)、さらにはコンバージョンといったユーザー行動に直結する指標にフォーカスすべきでしょう。
また、「検索結果100位まで」という広い範囲を見るのではなく、上位10位以内でどれだけ成果を出せるかに注力する流れが強まると考えられます。
Webuzz編集部の今後の見解
今回の「num=100」廃止は、Googleが公式にサポートしていない使い方を是正したという側面が強いと見ています。
長年、多くのSEOツールは非公式な“抜け道”を利用してきましたが、Googleがこれを封じたことで、今後はより健全な方法でのデータ取得が求められるでしょう。
この変更は、一見すると不便でコスト増につながる「改悪」のように感じられるかもしれません。
しかし、これはSEO担当者が本当に重要な指標に目を向ける良い機会でもあります。
これまで100件表示で膨らまされていたインプレッションは、実ユーザーの行動を反映していないノイズでした。
このノイズが除外され、サーチコンソールのデータがより現実に即した形になったと考えれば、むしろデータ品質の向上だと言えます。
SEOは常にGoogleの動向に合わせて変化していくものです。
今回の件は、「表面的な数字を追うのではなく、クリックやコンバージョンといったビジネスに直結する真のKPIにフォーカスすべき」という、基本的な心構えを改めて問い直すきっかけになるのではないでしょうか。
とはいえ、新規立ち上げサイトなどのアクセスが少ないサイトにとっては希少なデータがさらに少なくなり、立ち上げ初期の分析や対策がしづらくなるのも事実です。
ここは現場の担当者からも「実感として不便になった」という声が出ています。
まとめ
2025年9月中旬、「検索結果を100件まとめて表示できるパラメータ(num=100)」が突如として廃止されました。
これにより、検索順位チェックツールやサーチコンソールの数値に大きな影響が生じ、SEO業界全体に波紋が広がっています。
検索順位チェックツールでは、データ取得の効率が大幅に低下し、コストや処理時間の増加という課題が浮き彫りになりました。
また、サーチコンソールではインプレッションの急減や平均順位の見かけ上の改善といった変化が確認され、データの解釈に注意が必要になっています。
今回の「num=100」廃止は、単なるツールの仕様変更にとどまりません。
これはSEO担当者が「検索順位を100件まで追う時代」が過去のものになったことを意味しています。
これからは、Googleのサーチコンソールデータもより現実に即した形になるため、表面的な数値に惑わされず、クリック数・CTR・コンバージョンといった実ユーザーの行動を示す指標を重視することが求められます。
SEOは常に変化するGoogleの動向に合わせ、より精度あるデータと実ユーザー行動に基づく分析へとシフトしていく必要があります。
今回の件は、その時代の転換点を示す出来事だと言えるでしょう。